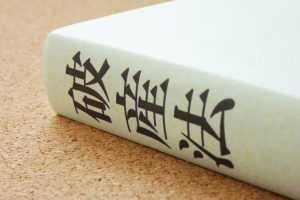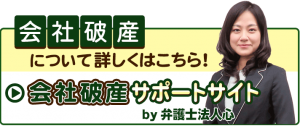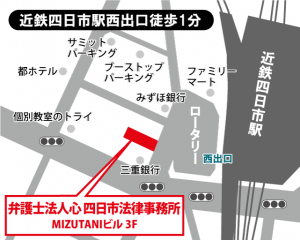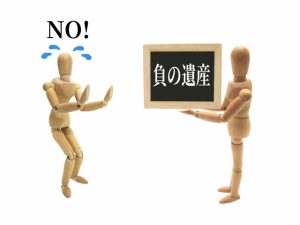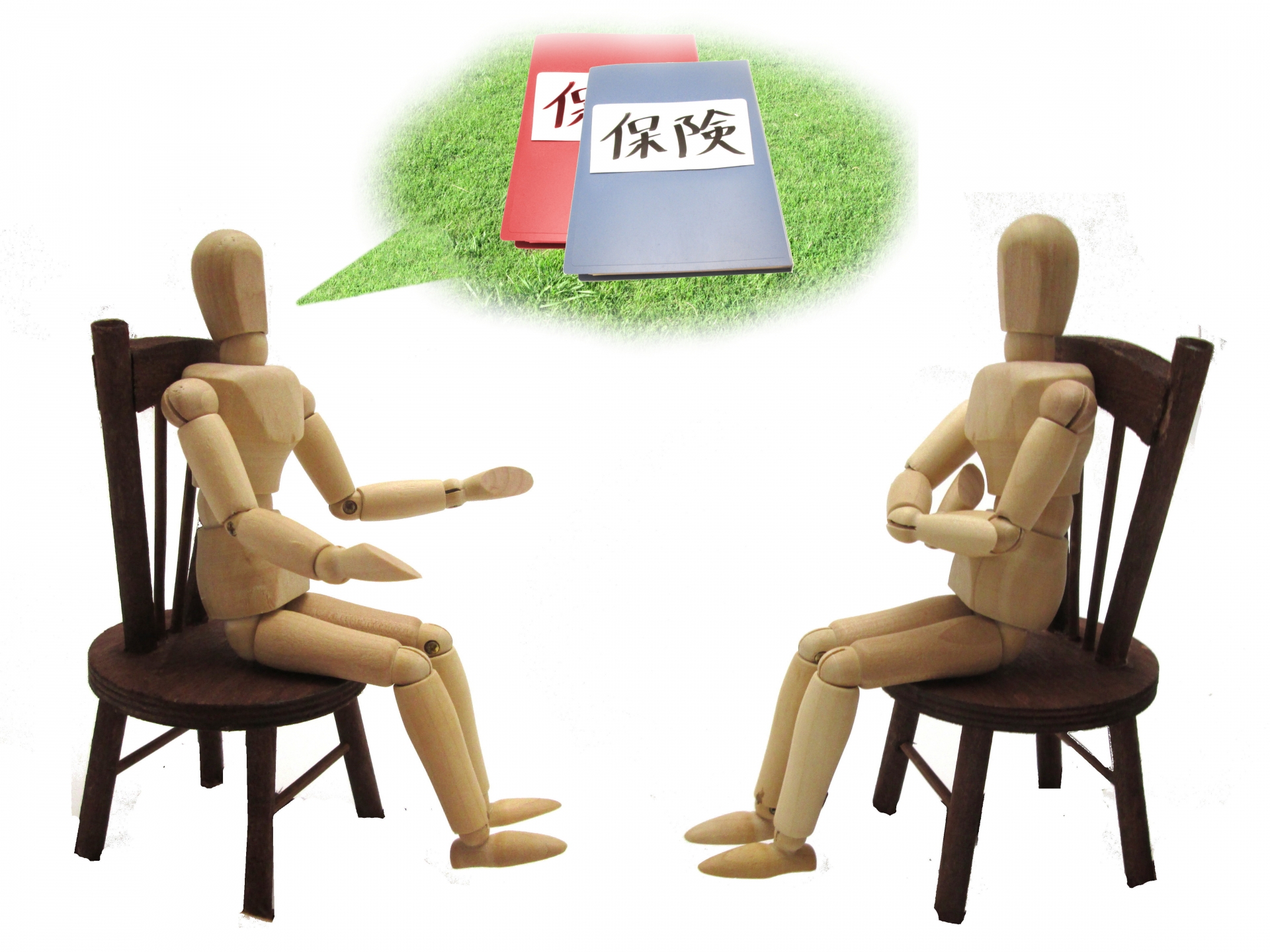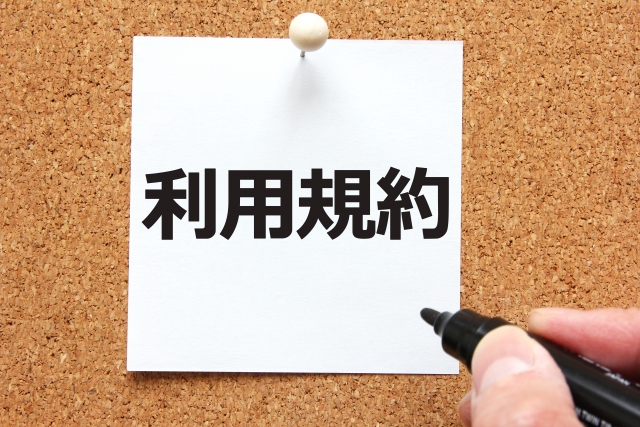1 強制執行が必要となる場面
⑴ お金を返してもらえない場合にはどうする?
例えば,貸したお金を返してくれない人がいるとします。
督促しても返してくれない場合,どうすればよいのでしょうか?
日本では,債務者の家に立ち入って無理やりお金を持ってくるなどといった法律の手続きを踏まない実力行使(自力救済などと言われます。)は,認められていません。
債務者がお金を返してくれない場合には,基本的に,訴訟等の裁判所での手続きが必要となります。
⑵ 裁判してもお金を返してくれない場合には強制執行
それでは,訴訟をして勝訴判決を得たとします。
これで債務者がお金を返してくれればよいのですが,それでも返してもらえない場合があります。
そのような場合に,「強制執行」という方法をとることになります。
2 強制執行とは
強制執行とは,裁判所を通じて債務者の財産を差し押さえて,お金に換え,債権者がそのお金の配当を受けるという手続きです。
強制執行をするためには、確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促などの「債務名義」といわれる文書が必要です。
3 強制執行の種類
⑴ 金銭執行・非金銭執行
強制執行は,金銭執行と非金銭執行に分かれます。
⑵ 金銭執行
金銭執行とは,金銭の支払いを受けるための手続きです。
お金を返してもらえないといった場合には,金銭執行をすることになります。
金銭執行は,何に対して執行するかという観点から,不動産執行,船舶執行,動産執行,債権執行に分かれます。
債務者がお金を返してくれないから,債務者の土地や建物を差し押さえて競売にかけるというのは,不動産執行です。
債務者の給料を差し押さえるという場合もありますが,これは債権執行です。
なお,給料は民事執行法で差押禁止債権とされており,給料の4分の3(給料が33万円を超える場合には33万円)については差押えをすることができません。
⑶ 非金銭執行
非金銭執行は,金銭の支払いを目的としない執行手続きです。
例えば,アパートの大家さんが,賃貸借契約が終了した後も出ていってくれない人がいて困っていたとします。
大家さんは,出ていってくれない人を無理やり力で追い出すことは法律上認められておらず,このような場合には,建物明渡請求訴訟をして勝訴判決をとった上で,強制執行をすることになります。
このような場合には,お金の支払いではなく,建物の明渡しを目的としているので,非金銭執行になります。
4 強制執行の費用等
どのような手続きをとるかによって異なります。
また,裁判所によっても異なる場合があります。
以下は,名古屋地方裁判所における不動産競売の場合の費用です(※例外や変更の可能性もあります。)。
①申立手数料 4000円
②登録免許税
請求金額(1000円未満切捨て)×4/1000=登録免許税額(100円未満切捨て)
③予納金 原則70万円
また,弁護士に強制執行の申立てを依頼する場合には,弁護士報酬もかかります。
5 まとめ
以上,簡単に強制執行について見てきました。
債務者が自発的にお金を支払ってくれない場合,法律に基づいて債権を回収するためには,お金も時間もかかってしまうという場合が多くあります。
私も弁護士として債権回収のご相談を受けることがありますが,訴訟では勝てる見込みが大きくても,相手にめぼしい財産が無さそうな場合には,強制執行しても空ぶってしまい,費用も時間も無駄になってしまう可能性をお伝えしなければならないこともあります。
また,債権の金額が少額の場合には,債権を回収できたとしても,弁護士報酬が同等かそれ以上にかかってしまったら経済的には意味がないので,なかなか難しいところです。
参考リンク:裁判所・民事執行手続