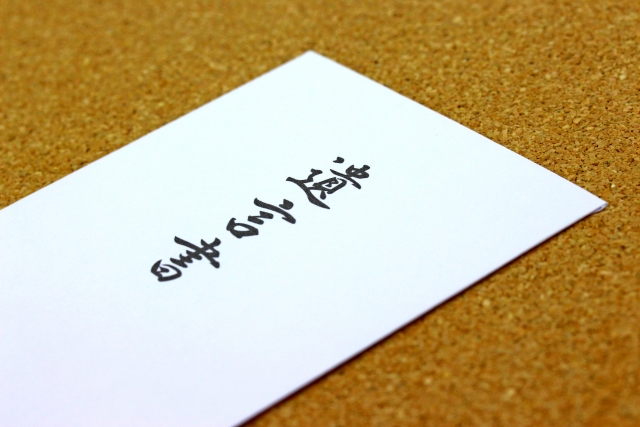1 正当防衛とは
刑事事件のニュースや刑事ドラマで,時々,「正当防衛」という言葉がでてきますが,どのような場合に正当防衛が認められ,正当防衛となるとどうなるのかご存知でしょうか。正当防衛は,簡単に言うと,相手が攻撃してきた場合に,自分の身を守るために反撃するというものです。
刑法には,36条1項に正当防衛についての定めがあり,「急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。」とされています。
2 正当防衛となるとどうなる?
刑法では,正当防衛の場合には,「罰しない」とされています。
この「罰しない」の意味について,刑法学上は,違法性が阻却される(なくなる)と考えるのが通常です。
違法性がないと犯罪は成立しませんので,犯罪にならないということです。
3 正当防衛となるための要件
⑴ 「急迫不正の侵害」
まず,正当防衛となるためには,「急迫不正の侵害」が必要です。
例えば,あらかじめ相手がいつどこで襲ってくることがわかっており,この機会に相手に危害を加えてやろうと思い反撃の準備をしていたような場合には,「急迫不正の侵害」は認められず正当防衛にはなりません。
⑵ 「自己又は他人を防衛するため」
他人の権利を守る場合でもよいため,例えば,仲間を助けようとした場合でも正当防衛になります。
⑶ 「やむを得ずにした行為」
正当防衛となるためには,「やむを得ずにした行為」でなければなりません。
例えば,逃げようと思えば問題なく逃げられたのに,あえて反撃したような場合は,「やむを得ずにした行為」とはいえません。
また,素手で殴りかかってきた相手に対して,拳銃で反撃したような場合も,体格差や状況にもよりますが,基本的には「やむを得ずにした行為」とはいえないと考えられます。
4 刑事事件で正当防衛を主張したい場合にはどうすべきか
正当防衛が認められるためには,正当防衛を基礎づける事実関係を主張・立証していく必要がありますので,弁護士にしっかりと相談することが重要です。