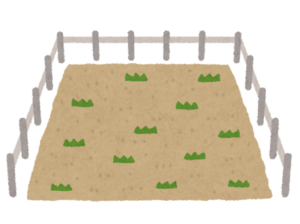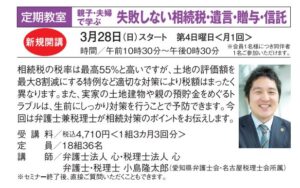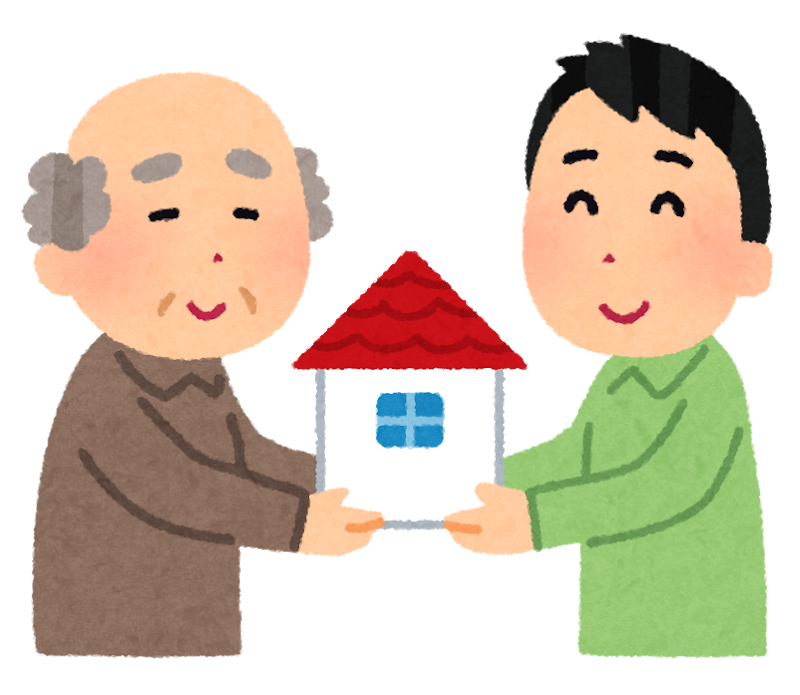これまで、相続した土地の登記は義務ではありませんでしたが、相続登記が義務化されます。
これは、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し、というテーマですでに法務省や国土交通省で具体的な検討がすすんでおり、5年以内には関連するすべての法令が施行される予定です。
具体的には、
①所有者が不明の土地・建物を管理するための制度を創設、
②共有不動産の利用を円滑化する仕組みの整備、
③相続開始から10年以上経過した遺産分割制度の見直し、
④隣地所有者がわからない場合のライフライン設備の設置に関する制度の整備、
⑤管理不全土地・建物の管理制度の創設、
などの制度が整備されます。
なかでも、①所有者が不明の土地・建物を管理するための制度は、不動産を相続するすべての人に関係します。
これまでは、不動産を相続した場合でも、相続登記をする義務そのものはありませんでした。
不動産を相続した後、登記の手続き費用がかかるとの理由で相続登記をしていない方もたくさんいましたし、現在もいます。
そのため、登記名義人は既に亡くなっているけれども、登記に記載された氏名や住所がなくなった方のままになっており、その相続人に連絡を取ることもできないなど、登記名義人と実際の所有者が異なる場合に土地の売買ができなくなってしまう、ということがありました。
このような場合、単に不経済というだけでなく、隣の建物が荒廃していて非常に危ないけれども、連絡をとることすらできない、といったことがありました。
今回の法整備では、相続登記を義務化することで、このような自体の発生を防ぐことが目的になっているようです。
相続人に相続登記を行わせるだけでなく、登記官の職権による手続きも一部認めるようです。
5年以内には、関連する法令が施行されるようですので、今後の動きを注視したいと思います。
登記のご相談は、司法書士だけでなく弁護士にご相談いただくことも可能ですので、相続に詳しい弁護士にご相談ください。